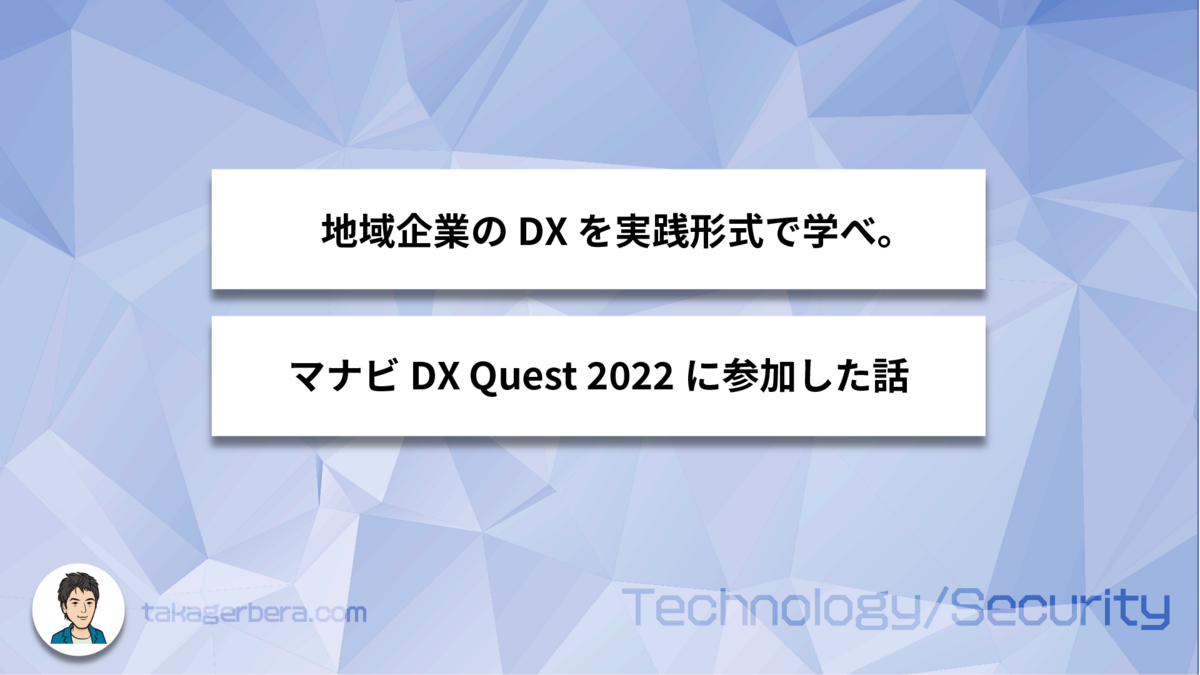 < 2023年4月9日公開、2023年6月18日更新 >
< 2023年4月9日公開、2023年6月18日更新 >
経済産業省と情報処理推進機構 (IPA) が開催する「マナビDX Quest」の2022年度プログラムに参加し、一連のコンテンツを完走しました。
私は昨年の9月から今年の1月にかけて、後述する「ケーススタディ教育プログラム」と「現場研修プログラム」の両方に参加しています。本業と並行して本プログラムを走っていたのですが、きちんと振り返る機会がなかったので、振り返りついでに記事に起こしたいと思います。
プログラムの概要
「マナビDX Quest」は、経済産業省が提供するデジタルトランスフォーメーション (DX) の学習に関する情報を発信するプラットフォーム「マナビDX (マナビ・デラックス)」で展開される、実践型のデジタル推進人材プログラム。経済産業省がかつて展開していた「AI Quest」を前身としており、領域を「機械学習・人工知能 (AI) 領域」から「DX全般」に拡大しているのが大きな違いです。
プログラムは大きく分けて「ケーススタディ教育プログラム」と「現場研修プログラム」の2種類のコンテンツで構成されており、一連の流れを通じて人工知能 (AI)・機械学習もしくはデータサイエンスに関する能力と、DXコンサルテーションに関する能力を学ぶことができます。得られる能力のうち「人工知能 (AI)・機械学習もしくはデータサイエンスに関する能力」については、ケーススタディ教育プログラムで選択した課題によって変わります。
私が参加した2022年度プログラムは、学生・社会人を問わず広く参加を募っていたとともに、充実の内容にも関わらず参加費無料という大盤振る舞い*1。2022年初頭に、時の政権がデジタル人材育成に4000億円もの莫大な予算を投入することが報じられ、リスキリングなどのキーワードと並んで話題になったことが記憶に新しいですが、その結果の一つが恐らくこれか...と思ったのが正直なところ。しかし、属性・業界を跨いだ多様な交流が生まれるのは悪いことではないので、いち参加者としてうまく使わせてもらった格好です。
この記事を書いている2023年4月現在、経産省から実施報告書が公開されており、その内容によると両コンテンツ合わせて2500人近くの方が参加した模様。報告書の内容を見る限り、広くDXに触れてもらうという観点では、一定の成果を果たしたものと思われます。
「ケーススタディ教育プログラム」について
ここからは、先ほど触れた2種類のコンテンツについて説明をしていきます。
まず「ケーススタディ教育プログラム」は、事務局から与えられたケーススタディ課題を指定期間内で解く座学中心のプログラム。2022年度は前期と後期の最大2回、ケーススタディ課題に挑戦することができました。1回のケーススタディ課題に与えられている期間は9週間ほど。期間中に5〜6回設けられているマイルストーン毎に指定の内容を提出することで、課題が進行していきます。
ケーススタディ課題は、事務局から与えられたデータや補助教材を使いながら独力で行うことを基本としているものの、必要に応じて参加者用Slack内で相互に教え合い・学び合いながら進行可能。そのため、IT分野の経験の浅い学生や非IT系職種などデジタル化スキルに不安が残る方でも、周囲からのフォローが受けられる構造となってるのが特徴です*2。
教材のテーマは「AI導入プロジェクトを一気通貫で疑似体験する内容」と「データドリブンなDX推進を一気通貫で疑似体験する内容」の2種類があり、各回で参加者の希望に沿うものを選択できます。一部のケーススタディ課題は、先述した「AI Quest」で行われた企業研修プログラムでの取り組み内容がベースになっており、自主学習であってもDXのリアルを感じてもらおうという意思が感じられました。
取り組んだケーススタディ課題は、各マイルストーンでの提出物および提出状況、中間と最後に行われる参加者間レビューの結果に基づき評価され、最後に「Gold」もしくは「Silver」の修了証が付与されます。それぞれの発行基準は以下の通り。
- 修了証「Gold」: 各マイルストーンごとに指定されている提出物(中間と最終の相互レビューも含む)を、全て締め切りに遅延なく提出・完遂した
- 修了証「Silver」: 1つ以上の提出物に遅延があったものの、課題の提出自体は全て行われた
課題の評価は前期と後期でそれぞれ行われるため、最大で修了証を2つもらうことが可能。このほかにも、課題ごとに相互レビュー結果に応じた順位付けがなされ、全体の上位5%に食い込むとその方は「総合優秀賞」として表彰されます。また、参加者相互レビューで上位20%以内の順位に入ると、中間であれば「AI優秀賞」もしくは「DS優秀賞」として、最終であれば「プレゼン優秀賞」としても表彰されます。
しかし、回答例や他者の内容からのコピペなど、提出物のクオリティが著しいレベルで趣旨にそぐわない場合、上記を満たしていても修了証が付与されないことがあるとのこと。先述の実施報告書に、2022年度のケーススタディ教育プログラムの修了率は約6割の記載があることから、これは決して嘘ではなさそうです。参加者間の相互レビューによる自浄作用が働いていると考えられる一方、業務都合などで途中脱落した参加者もそれなりにいると思われるので、今後参加しようと考えている方は、せめて実施スケジュールをよく確認した方がいいかもしれません。
なお、2022年度プログラムで出されたケーススタディ課題の一部は、サンプル問題として上述した報告書と同じページより公開されています。
ケーススタディ教育プログラムの表彰結果と、その進め方
私は昨年度プログラムのケーススタディ課題を前期と後期の2回、テーマはいずれも「データドリブンなDX推進を一気通貫で疑似体験する内容」を選択して受けています。そして、前期・後期とも、全ての提出物を遅延なく提出・完走したため修了証「Gold」を取得し、前期のケーススタディ課題ではなんと「総合優秀賞」のひとりに選ばれました。後期のほうも「プレゼン優秀賞」のひとりに選ばれているので、プログラム全体を通じ、IT人材として十分な能力があることを示すことができたのではないかと思います。
職種が変わったため、コードを書いたり、データの分析・解析を行ったりする場面から離れて久しく、前線で活躍されている方々には敵わないと正直思っていました。ですが、この結果を見て、自身のITスキルが「まだまだ捨てたもんじゃない」レベルであると再認識し、これからの自信に繋げられました。相互評価していただいた皆さん、ありがとうございます。


課題の遂行は、提出物にちょっとした箔を付ける工夫にAutoMLサービスを使った以外は、データ分析をExcelで、提出物の作成をPowerPointで行う「非プログラマースタイル」で実施。Jupyter Notebookぐらい使えれば楽だろうな...とも思いましたが、Pythonの学習し直しにかかる時間などを嫌がったため非プログラマースタイルで完遂した格好です。
1個の提出物にかけた時間は概ね10時間程度。2回あったデータ分析結果を提出物に指定された回のみプラス4、5時間という感じだったので、ケーススタディ全体で70 〜 80時間前後といったところ。このあたりは本業の都合や参加者当人のスケジュールに拠るところが大きいと思いますが、他の参加者が行ったSlackの投稿を見る限り、私は時間的余裕が比較的ある方だったと思います。11月ぐらいから後期ケーススタディ教育プログラムと現場研修プログラムが同時並行で走っていたのですが、これらの両立を考えた場合、ケーススタディ側はちょっと余裕があるぐらいじゃないと正直辛かったです*3。
「現場研修プログラム」について
続いて「現場研修プログラム」ですが、前期のケーススタディ課題を完走した参加者と「AI Quest」に参加経験のある方を対象に、チームで実際の中小企業のDX課題について取り組むプログラム。全国から参加したマナビDXの取り組みやその趣旨に賛同するDXへ取り組む意思のある地域企業が、全国からオンラインで参加している参加者で構成されたチームとともに、実際の事業課題のもとDXを推進するのが特徴です。
私は後期のケーススタディ課題と並行して、こちらのプログラムにも取り組ませていただきました。企業と取り組んだ内容は、マナビDX Quest事務局と結んだ秘密保持契約 (NDA) の都合で割愛させていただきますが、協働先企業が属する業界特有の知識が不足する中、チームの皆さんや研修先企業の担当者との協力もあり、何とか完走することができました。
年度末にかけて本業が忙しくなる中、週1回行われた協働先企業との打ち合わせ、それ以上の頻度で行われるチームミーティング、そしてチーム内での個人ワークを並行して行うのは正直大変でしたが、自らの持ち味を出しつつ成果に結びつけることができたのは、全ての関係した方のおかげです。私がマナビDX Questに参加する動機がこの企業研修プログラムの存在でだったため、この場を借りて御礼申し上げます。ありがとうございました。
現場研修プログラムを完走すると、以下のオープンバッジがもらえます。ケーススタディ教育プログラムの「表彰」に相当する箇所には、取り組み内容と協働先企業が属する業界が記録。当該業界の業務経験を持っていることを客観的に証明できるのは、転職を考えている方にとってうれしいかも。

なお、現場研修プログラムでの取り組みは、全チーム分、上述した報告書と同じWebページより報告書が公開されています。チームのスキル構成や大まかな進め方なども掲載されているので、今後参加される方は参考になるかと思います。
感想・総評
マナビDX Questは、前期のケーススタディ課題から企業研修プログラムの終了まで約半年に渡る長い取り組みでしたが、取り組んだことの苦労に見合う多くの経験が得られました。
特に企業研修プログラムでは、多様かつ実力に富んだチームのメンバーに恵まれたと同時に、彼らから影響を受けるだけでなく、私からも発信することで何らかの貢献を果たせたことが一番の思い出であり、誇りです。普段、仕事やプライベートでは絶対に絡むことの出来ない人と、偶発的な出会いによって成果を生み出せる柔軟性と瞬発力はこういったものでしか鍛えられないので、貴重な経験だったと思っています。
今年度以降も開催されるかは分かりません2023年度も開催が決定しておりますが、機会があればまた挑戦したいですね。